⚡ 衝撃のニュース
「AI が作った画像だから著作権はない」――その常識が、2025年11月20日に覆されました。全国初の摘発で明らかになった、驚きの判断基準とは?
2025年11月20日、生成AI業界に激震が走りました。千葉県警が、生成AI画像の無断複製で著作権法違反の容疑により、神奈川県の27歳男性を書類送検したのです。
「AIが作った画像に著作権なんてあるの?」――多くの人がそう思うはずです。実は、これまで日本では「AI生成画像の著作権」が認められて摘発された事例はありませんでした。
しかし今回、千葉県警は明確に「AI画像にも著作権がある」と判断しました。この判断は、生成AIを使っている全ての人に影響を与える可能性があります。
「自分のAI利用は大丈夫?」「どんな使い方が違法になるの?」――この記事では、全国初の摘発事例から、私たちが知っておくべき生成AIと著作権の新常識を解説します。
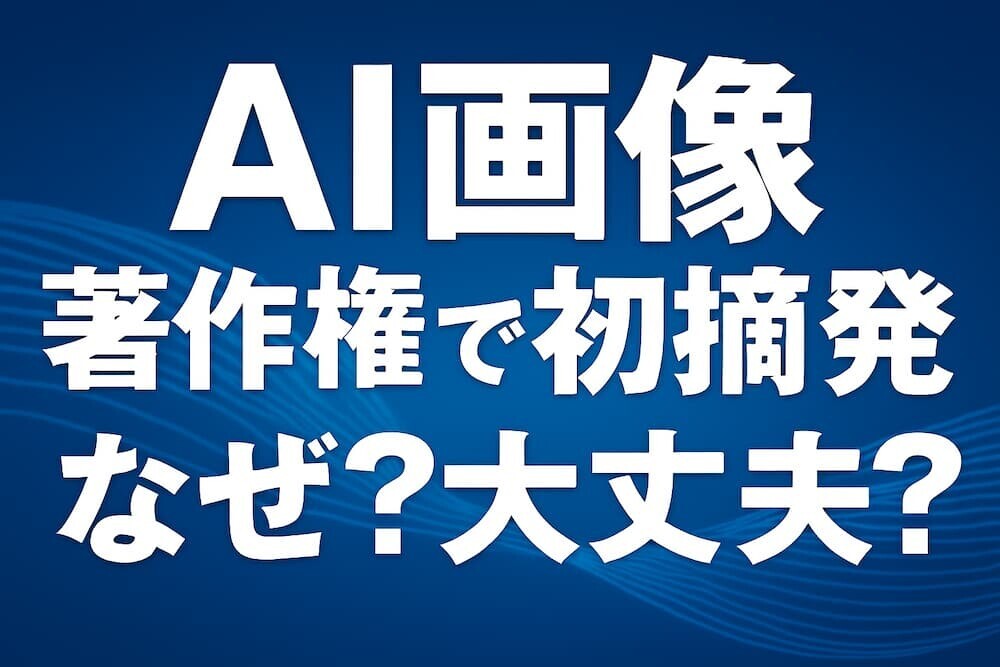
📋 この記事でわかること
🚨 全国初!AI画像で著作権法違反の摘発
読売新聞の報道によると、2025年11月20日、千葉県警は神奈川県大和市の27歳男性を著作権法違反(複製権侵害)の疑いで千葉地検に書類送検する方針を固めました。
事件の概要はこうです。2024年8月下旬頃、この男性は千葉県の20代男性イラストレーターが画像生成AI「Stable Diffusion」を使って制作した画像を無断で複製し、自身が販売した書籍の表紙に使用したとされています。
📌 重要ポイント
被害者が警察に相談したことで捜査が始まり、今回の書類送検に至りました。千葉県警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けています。
これが何より驚きなのは、AI生成画像に著作権があると判断して著作権法違反で摘発するのは全国で初めてだということです。
「AI画像に著作権なんてあるの?」という疑問が多くの人の頭に浮かんだはずです。実は、これまでAIが生成した画像については「著作権があるのか、ないのか」がはっきりしていませんでした。
AI生成画像を巡っては、これまでも様々な問題が指摘されてきました。例えば、2025年1月には神奈川県警が画像生成AIで「エヴァンゲリオン」のポスターを作成・販売した男性2人を書類送検しています。
しかしこの事例は、既存のアニメキャラクターを模倣したことが問題でした。一方、今回の事件は「AI生成画像そのもの」に著作権があると認めた点で、まったく異なる意味を持ちます。
では、なぜ今回、AI画像に著作権が認められたのでしょうか?次のセクションで詳しく見ていきましょう。
🤔 なぜAI画像に著作権が認められたのか?
今回の摘発で最も注目すべきポイントは、千葉県警が「AI生成画像も著作物になり得る」と判断したことです。その判断の鍵となったのが、被害者の創作過程でした。
読売新聞の取材によると、被害者の男性はプロンプト(AIへの指示文)を2万回以上も入力していたことが分かっています。
💡 2万回という数字の意味
1日に100回指示を出し直したとしても、200日かかる計算です。それだけの試行錯誤を重ねて、理想の画像を作り上げていったのです。
「AIが作った」のではなく、「人間がAIに何度も何度も指示を出して作らせた」――この違いが重要でした。
文化庁が公表している「AIと著作権に関する考え方」では、AI生成物が著作物に当たるかどうかを判断する際、以下の要素を総合的に考慮するとしています:
- ✅ AIへのプロンプト(指示)の分量と内容
- ✅ 生成の試行回数
- ✅ 生成後の人間による加工・編集の有無
著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。今回のケースでは、被害者が膨大な試行錯誤を重ねて具体的な指示を繰り返したことで、「人間の創作性が十分に反映されている」と判断されたわけです。
AI と著作権に詳しい福井健策弁護士(第二東京弁護士会所属、米ニューヨーク州弁護士登録)は「プロンプトで具体的な指定を十分にしていれば著作物になり得る」と指摘しています。
福井弁護士によると、生成AIにあいまいな指示をすれば生成物は多様になり、作り出されるものを予測するのは難しくなります。一方で、詳細で具体的な指示をすればするほど、生成物は作者の創意に沿い、意図した表現の画像が作り出されるといいます。
つまり「人が結果を具体的に予測して指示を出しているかどうか」が著作権の有無を判断する重要なポイントなのです。
🌍 国際比較:国によって180度異なる判断
ただし、この判断は国によって大きく異なります。
米国著作権局は2023年2月、生成AIで作成した漫画のイラストについて著作権登録の申請を却下しました。生成AIがどのようなものを作成するか予測は不可能で、「人がコントロールしているわけではない」という理由からです。
一方、中国の北京インターネット法院は2023年11月、生成AI で作った画像の無断使用を著作権侵害と認める判決を出しました。「原告(作者)はプロンプトの選択などで相当の知的労力を費やした」と評価したのです。
日本の今回の判断は、中国の判例に近い考え方だと言えます。「人間がどれだけ創作的に関わったか」を重視する方向性です。
さて、ここまでの説明で「AI画像に著作権が認められる可能性がある」ことは理解できたと思います。では、普通にAIを使っている私たちは、どんな場合に違法になってしまうのでしょうか?
⚠️ あなたのAI利用は大丈夫?違法になる3つのケース
「自分もAI画像を使ってるけど、大丈夫かな…」と不安になった人もいるかもしれません。でも安心してください。普通に使っている分には、ほとんどの場合問題ありません。
まず大前提として、著作権法では「私的使用のための複製」は認められています。つまり、個人的に楽しむために AI 画像を生成することは全く問題ないのです。
✅ 安心してください
個人的な利用、趣味での使用、SNSへの投稿など、商用目的でなければ基本的に問題ありません。
問題になるのは、主に以下の3つのケースです。
❌ ケース1:他人のAI生成画像を無断で商用利用する
今回の事件がまさにこれです。他の人が苦労して作ったAI画像を、許可なく自分の商品(書籍の表紙など)に使うのは完全にアウトです。
これは普通の写真やイラストと同じです。「AIが作ったから誰のものでもない」というわけではありません。
❌ ケース2:既存の作品に酷似したAI画像を商用利用する
有名なアニメキャラクターや、特定のアーティストの作風をそっくりそのまま真似したAI画像を作って、それを販売したり広告に使ったりするケースです。
商用利用に関する解説記事によると、AIが学習に用いたデータに既存の著作物が含まれている場合、AIが出力した画像が既存作品と酷似してしまい、知らずに著作権を侵害してしまう可能性があります。
特に、既存作品を模倣するようなプロンプトやスタイル指定を行った場合、そのリスクは高まります。
❌ ケース3:商用利用禁止のAIサービスで作った画像を商用利用する
これは著作権法というより、サービスの利用規約違反になるケースです。一部のAI画像生成サービスは、無料プランでの商用利用を禁止しています。
例えば、Midjourneyの無料版は以前、商用利用ができませんでした(現在は無料版自体がなくなっています)。
📊 著作権侵害の2つの判断基準
類似性:既存の著作物と似ているかどうか
依拠性:既存の著作物を元にして作ったかどうか
この2つが両方とも認められると、著作権侵害になる可能性が高くなります。
では、どうすれば安全にAI画像を使えるのでしょうか?
次のセクションでは、安全にAI画像を使うための具体的な対策を5つ紹介します。
🛡️ 安全にAI画像を使う5つの対策
AI画像を安全に使うための対策を、具体的に5つ紹介します。これらを守れば、リスクをかなり減らすことができます。
1️⃣ 商用利用OKのサービスを選ぶ
まず大前提として、商用利用が明示的に許可されているAIサービスを使いましょう。商用利用可能なサービスをまとめた記事によると、以下のようなサービスが商用利用に対応しています:
- Adobe Firefly:オープンライセンスまたは許可取得済みの素材のみを学習元として使用
- Shutterstock AI:すべてライセンス済み素材で、知的財産権のクリアランスが保証されている
- Leonardo AI:有料プランでは完全な所有権・著作権を保持できる
これらのサービスは、著作権侵害のリスクを減らすための仕組みが組み込まれています。
2️⃣ 有名作品・キャラ名をプロンプトに入れない
「ピカチュウみたいなキャラクター」「ジブリ風の背景」など、特定の作品名や有名キャラクター名をプロンプトに入れるのは避けましょう。
多くのAIサービスでは、有名キャラクター名を入力するとエラーになったり、自動的に修正されたりする仕組みが入っています。でも完璧ではありません。
代わりに「かわいい黄色い動物キャラクター」「緑豊かな自然の風景」など、一般的な表現で指示を出すようにしましょう。
3️⃣ 生成後に類似チェックを行う
AI画像を商用利用する前に、既存の著作物と似ていないかチェックすることが重要です。
Googleの画像検索で類似画像を探したり、専門的なチェックツールを使ったりする方法があります。特に商用利用する場合は、このステップを省略しないようにしましょう。
4️⃣ 利用規約を必ず確認する
これは基本中の基本ですが、意外と読まずに使っている人が多いです。
AIサービスの利用規約では、以下のような点を必ず確認しましょう:
- 商用利用が許可されているか
- 生成した画像の著作権は誰に帰属するか
- 禁止されている用途はないか
- 年齢制限や地域制限はないか
利用規約は更新されることもあるので、定期的に確認することをおすすめします。
5️⃣ 生成画像に自分の加工・編集を加える
AI が生成した画像をそのまま使うのではなく、自分で加工や編集を加えることで、オリジナリティが高まります。
例えば:
- 🎨 色調を調整する
- 📝 テキストやロゴを追加する
- 🔗 複数の画像を組み合わせる
- ✏️ 細部を手作業で修正する
こうした加工を施すことで、「人間の創作性が加わった作品」としての性格が強くなり、著作権的にもより安全になります。
この5つの対策を守れば、AI画像を安全に活用できます。
でも、今回の摘発は単なる一つの事件ではありません。これからのAI業界全体、そしてクリエイターの働き方にも大きな影響を与える可能性があります。
🔮 今後のAI業界・クリエイターへの影響
今回の全国初の摘発は、AI業界とクリエイター業界の両方に大きな影響を与えると考えられます。
👥 クリエイターへの影響:権利保護の前進
これまで「AI が作った画像は誰のものでもない」と思われがちでした。しかし今回の摘発により、「十分な創作性があればAI生成画像にも著作権が認められる」ことが明確になりました。
これは、AIを使って作品を作るクリエイターにとって朗報です。自分が時間をかけて作った AI 画像が、他人に勝手に使われる心配が減るからです。
ただし、逆に言えば「他人のAI作品を無断で使ったら訴えられる可能性がある」ということでもあります。
🏢 AI企業への影響:コンプライアンス強化
AI 画像生成サービスを提供する企業にとっても、今回の摘発は重要な転換点です。
日本経済新聞の報道によると、AI と著作権に詳しい福井健策弁護士は「海外ではAI企業がクリエーター側と契約する動きがある。日本でもルールの検討は続けながら、協業を模索する動きが広がるのではないか」と推測しています。
実際、海外では AI 企業とクリエイターが協力関係を築く事例が増えています。たとえば、クリエイターが自分の作品を学習データとして提供する代わりに、適切な対価を受け取る仕組みなどです。
⚖️ 法改正の可能性:AI時代に対応した著作権法
2025年の展望をまとめた記事では、文化庁の「AI時代の知的財産権検討会」が2024年に中間とりまとめを公表し、生成AIと著作権に関する法的課題の整理が進んでいると報告されています。
今後、以下のような点で法改正やガイドラインの策定が予想されます:
- AI学習のための著作物利用に関する権利制限規定の明確化
- 人間とAIの協働による創作物の著作権保護のあり方
- AI生成コンテンツの出所表示や透明性確保のルール
- 権利者とAI開発者・利用者のバランスを取るための制度設計
💻 利用者への影響:より明確なルール
私たち一般のAI利用者にとっては、ルールが明確になることで「何をしていいのか、何がダメなのか」が分かりやすくなります。
現状では「グレーゾーン」とされていた部分が多かったのですが、判例が蓄積されることで、より安心してAIを使えるようになるでしょう。
🤝 「AI vs クリエイター」ではない未来
「AIによってクリエイターの仕事が奪われる」という対立構造で語られることが多いですが、実は違う未来も見えてきています。
AI は、クリエイターの創作を助けるツールとして機能する可能性があります。AIで下描きを作り、人間が細部を仕上げる。AIでアイデアを出し、人間が最終的な判断をする――そんな協働の形が一般的になるかもしれません。
✨ 希望のメッセージ
今回の摘発は、AIとクリエイターが共存するための第一歩だと言えます。技術の進化は止まりません。法整備も徐々に進んでいくでしょう。変化に柔軟に対応しながら、AIという強力なツールを味方につけて、新しい創作の可能性を切り開いていく――そんな時代が始まっています。
📝 まとめ:AI画像と著作権の新常識
この記事の要点を整理します:
- 🚨 全国初の摘発:千葉県警が生成AI画像の無断複製で著作権法違反の容疑により男性を書類送検。AI生成画像に著作権を認めた全国初の事例
- 🔍 著作権が認められる理由:プロンプトを2万回以上入力するなど、人間が創作的に深く関わった場合、AI画像にも著作権が認められる可能性がある
- ⚠️ 違法になる3つのケース:①他人のAI生成画像を無断で商用利用、②既存作品に酷似したAI画像を商用利用、③商用利用禁止のサービスで作った画像を商用利用
- 🛡️ 安全に使う5つの対策:①商用利用OKのサービスを選ぶ、②有名作品名を避ける、③類似チェックを行う、④利用規約を確認する、⑤自分で加工を加える
- 🔮 今後の展望:クリエイターの権利保護が進み、AI企業との協業が増え、より明確なルールが整備されていく
あなたはAI画像をどのように使っていますか?今回の摘発を受けて、自分の使い方を見直してみるのも良いかもしれません。
生成AIは、私たちのクリエイティブな可能性を広げる革新的なツールです。正しい知識を持って使えば、誰もが安全に、そして創造的にAIを活用できる時代がやってきています。
❓ よくある質問(FAQ)
Q1. AI生成画像に著作権はありますか?
具体的なプロンプトを繰り返し入力するなど、人間が創作的に深く関わった場合、AI生成画像にも著作権が認められる可能性があります。今回の摘発では、プロンプトを2万回以上入力した画像が著作物と認定されました。
Q2. 個人的にAI画像を使うのは違法ですか?
個人的な利用や趣味での使用は全く問題ありません。著作権法では「私的使用のための複製」が認められています。問題になるのは、他人のAI画像を無断で商用利用する場合などです。
Q3. どのAI画像サービスなら商用利用できますか?
Adobe Firefly、Shutterstock AI、Leonardo AIなどが商用利用に対応しています。各サービスの利用規約を必ず確認し、商用利用が明示的に許可されているサービスを選びましょう。
Q4. 既存のキャラクターに似た画像を作るのは違法ですか?
有名なキャラクターや特定のアーティストの作風をそっくり真似したAI画像を商用利用すると、著作権侵害になる可能性が高いです。一般的な表現で指示を出し、特定の作品名やキャラクター名は避けましょう。
Q5. AI画像を安全に使うには何に注意すればいいですか?
①商用利用OKのサービスを選ぶ、②有名作品名を避ける、③生成後に類似チェックを行う、④利用規約を確認する、⑤自分で加工を加える、の5つの対策を守ることで、リスクを大幅に減らせます。
Q6. 今後AIと著作権の関係はどうなりますか?
文化庁で法的課題の整理が進んでおり、より明確なルールやガイドラインが策定される見込みです。AI企業とクリエイターの協業も進み、権利保護と技術発展のバランスが取れた制度設計が期待されています。